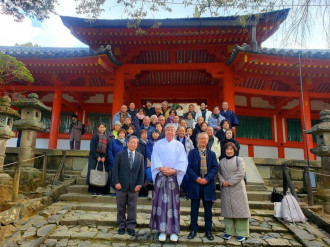奈良大学が8月30日から全3回で、高の原カルチャーサロン「江戸時代の文化とその広がり~怪談、出版、文芸から見る江戸時代~」を奈良市北部会館市民文化ホール(奈良市右京1、TEL 0742‐71‐5747)で開講する。
[広告]
江戸時代の怪談や出版事情、文芸作品を通じて、当時の人々がどのように文化を享受していたのかを紹介し、当時の人々の考え方や価値観について取り上げる。
8月30日の「石塔磨きの怪異-江戸のメディアと噂(うわさ)-」の講師は、文学部史学科の 村上紀夫教授。著書に「怪異と妖怪のメディア史」があり、江戸時代の庶民信仰や芸能史を研究している。1830年に江戸では、墓石がいつの間にか磨き上げられる事象が発生し、瞬く間にさまざまなうわさが広がったという。村上教授は「うわさの流布にどうメディアが関わり情報が構築されていったのかを伝える」と話す。
9月6日の「海賊版の時代-江戸の出版-」は永井一彰名誉教授、9月13日の「山東京伝の画業と文業-蔦屋重三郎との関係を通して-」は文学部国文学科 の中尾和昇准教授がそれぞれ担当する。
各日13時開始。受講無料。定員は100人。申し込みは奈良市北部会館市民文化ホールで受け付ける。締め切りは8月19日。